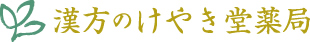中国医学と五行(ごぎょう)
中国に古くから伝わる考え方、哲学の一つに、五行学説があります。
五行学説は、宇宙に存在するすべての事物・事象を「木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい)」の五つの要素に分類し、それらの相互関係を通じて解釈する理論です。この学説は、臓腑(内臓)の働きや病理(病気の原因)の解釈にも応用され、人体のバランスを理解する上で重要な役割を果たします。例えば、五行(木・火・土・金・水)は五臓「肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)」や五季(春・夏・梅雨、季節のはざま・秋・冬)に対応し、それぞれが相生(助け合う)や相克(抑制し合う)という関係で結びついています。
この五行学説は古代中国の医学書「黄帝内経(こうていだいけい)」に記され、中国医学(漢方医学)の基礎として現在も使われています。
五行という言葉になじみがなくても、「五臓六腑(ごぞうろっぷ)にしみわたる」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。例えば、冷たいビールを一口飲んで「ああ、五臓六腑にしみわたる!」と声を上げる人もいますよね。この言葉は、五行の五臓に由来していると言われています。おいしい飲み物や食べ物を口にした際に、その感動が内臓全体、そして全身に染み渡るような感覚を表現しています。
五行学説で、宇宙に存在するすべての事物・事象を説明するということに、理屈っぽく、こじつけに感じる人もいると思います。しかし中国医学を理解する上では、五行説は基礎となりますし、紀元前の昔に考えられているのに、体系的、かつ理論的にまとめられています。黄帝内経を著した古代の中国の作者に、頭が下がる思いです。(岡北)