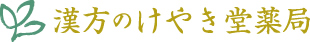中国医学と五行(ごぎょう)
中国に古くから伝わる考え方、哲学の一つに、五行学説があります。
五行学説は、宇宙に存在するすべての事物・事象を「木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい)」の五つの要素に分類し、それらの相互関係を通じて解釈する理論です。この学説は、臓腑(内臓)の働きや病理(病気の原因)の解釈にも応用され、人体のバランスを理解する上で重要な役割を果たします。例えば、五行(木・火・土・金・水)は五臓「肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)」や五季(春・夏・梅雨、季節のはざま・秋・冬)に対応し、それぞれが相生(助け合う)や相克(抑制し合う)という関係で結びついています。
この五行学説は古代中国の医学書「黄帝内経(こうていだいけい)」に記され、中国医学(漢方医学)の基礎として現在も使われています。
五行という言葉になじみがなくても、「五臓六腑(ごぞうろっぷ)にしみわたる」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。例えば、冷たいビールを一口飲んで「ああ、五臓六腑にしみわたる!」と声を上げる人もいますよね。この言葉は、五行の五臓に由来していると言われています。おいしい飲み物や食べ物を口にした際に、その感動が内臓全体、そして全身に染み渡るような感覚を表現しています。
五行学説で、宇宙に存在するすべての事物・事象を説明するということに、理屈っぽく、こじつけに感じる人もいると思います。しかし中国医学を理解する上では、五行説は基礎となりますし、紀元前の昔に考えられているのに、体系的、かつ理論的にまとめられています。黄帝内経を著した古代の中国の作者に、頭が下がる思いです。(岡北)

当店 LINE公式アカウント 「友だち」募集中

■ LINE【公式】漢方のけやき堂薬局 を運用しています。
「友だち追加」をしていただきますと、
月1回程度の健康情報をお受け取りになれます。
また、お問合せや、継続の方のカウンセリング日時変更などの連絡ツールとして利用いただけます。
⇒お客様と、当店スタッフ 1対1でチャット(文字で連絡のやり取り)が出来ます。
返信について:営業時間内に、1日数回メッセージをチェックしています。可能な限り、当営業日中に返信しています。
【【ご新規でカウンセリングを希望しているお客様へ】】
お手数をおかけしますが、別途連絡事項がありますので、「電話」でご予約の連絡をお願い申し上げます。
このボタン↓を押す、またはQRコードの読み取りで、当店の公式アカウントに「友だち追加」できます。

神経疲労が多くて、体が疲れやすい方へ 元気になる食べ物・過ごし方
寒さが少しずつ和らいで雨の降ることが続いています。暖かい陽気の後に、気温が下がることもあります。
つい先日、定期的に連絡下さっているお客様から相談があり、「体を温めるように気を付けているけれども、今、体が芯から冷えて温まってこないし、元気が出ない」とおっしゃっていました。
気温が上がったり下がったりを繰り返す中で、気温が下がった後、再び体温を上げて維持することに体力を使っているのでしょう。私のこれまで受け持ってきた健康相談の経験から、職場や家族など周囲の人に神経を遣うことが多い人は、肉体的な疲れも出てきやすい、と感じています。
東洋医学(中医学)では、気は、元気の気で、活動エネルギーの元であり、体を温める作用があるとしています。普段から、神経を使い、気をたくさん消費していることで、目には見えませんが、気の貯えが少なくなり、活動量は多くなくても、冷えやすく、心身もまた疲れやすいのだと思います。その結果、寒暖差があって元気が出ないのでしょう。
春の神経疲労への養生法は、体温を衣服で調節すること、体の内側からも温めて、血流を良くすることです。また、胃腸を整えておくことも、(体温調節に働く)自律神経の働きを良くすることに役立ちます。食べ物から気(栄養物)を受け取っているので、消化吸収の働きを良くしておくことが大事です。
胃腸の働きが弱っている場合は、他の症状を改善させることよりも胃腸を整えることを優先して考えましょう。近年、胃脳相関、腸脳相関があることが医学的に分かっていて、消化器の働きと精神活動、脳の神経の作用が互いにコミュニケーションを取り合っていることが注目されています。
春のお勧めの食材(食養生);
いらいらしやすい、気持ちが落ち込む、感情が乱れやすい場合: シソ、春菊、セロリ、三つ葉、かんきつ類(レモン、オレンジ)
よく眠れない場合、血を作る食べ物: アサリ、ナツメ
胃の調子が悪い場合: 豆類、じゃがいも、鶏肉、キャベツ
春のお勧めの過ごし方(生活養生);
日光浴、軽めの運動、湯船に浸かること、深い呼吸を心がけることです。
これらをまず出来ることから取り入れて、少しずつでいいので続けてみてください。
一般的に、胃腸の働きを整えて気を補う目的で用いる漢方薬は、補中益気湯、又は 帰脾湯(きひとう)、香砂六君子湯(こうしゃりっくんしとう)など。
いらいら、不安、不眠には、香蘇散(こうそさん)、又は 逍遥散(しょうようさん)、芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん)などです。
けやき堂薬局では、普段から自然薬や漢方で自然治癒力を上げておく体つくりをお勧めしています。そうしておくと多少、気などを消耗することがあっても、回復するのが早く、症状を改善する漢方を後から取り入れた場合も、少量で効果があらわれるでしょう。(例えば、春の頭が覆いかぶさるときにのむ、香蘇散など)
健康寿命を延ばしたい方、体調不良をお感じの方など、お気軽にご相談ください。
慢性的な症状の方は、まずご予約をお願いいたします。
カウンセリングで丁寧にお話を伺い、必要に応じて選薬いたします。(岡北)
公開日:3月7日